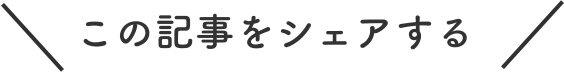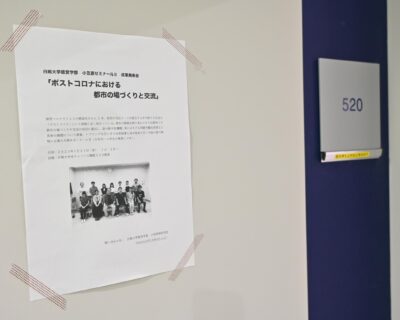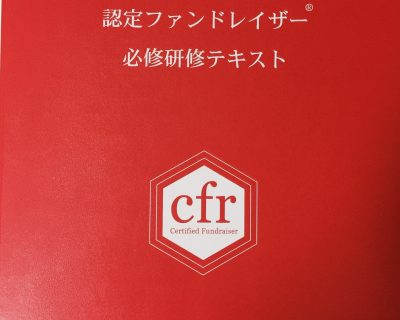「地域の大人は学生をなめるな」、白鴎大学小笠原ゼミ卒論発表会

2月8日、栃木県小山市にある白鴎大学経営学部小笠原ゼミの卒論発表会に参加しました。
去年も卒論発表会に参加し、ブログにまとめました。
今回発表する学生さんは2021年入学なので、大学生生活の半分くらいがコロナ下でした。行動制限によって学生生活が影響される中で学び続けた学生さんが、どんな卒論を書いたのだろうと楽しみに行きました。
発表内容は以下の通り。発表者名は省略します。
- 健康寿命の延伸と医療課題の解決へ導く地方での日本版CCRCについて ~栃木県那須町を例に~
- VTuber は地方創生に寄与できるか ~栃木県のメディアコンテンツの運用を提案する~
- 鹿沼市の「道の駅化」整備事業を進める上での課題について
- 地域におけるアイドルを活用した取り組みの意義について ~群馬県の事例を基に検討するアイドルによる地域の多様性創出の可能性~
- 消滅可能性自治体を広報からデジタル技術で存続させるために必要なこと ~栃木県那珂川町を例に~
- 地方自治体主導のリスキリングが持続可能な地域づくりに与える影響の考察 ~茨城県の事例より~
- 野球湯の経営における本拠地の重要性と理想の球湯について ~北海道日本ハムファイターズ・読売ジャイアンツの事例を基に~
発表は7分、質問タイムは8分、1発表につき15分の時間制限あり。タイムキーパーの学生さんがベルを持ち、制限時間30秒前で予告「チーン」、制限時間になると「チーンチーン」、制限時間を超えるとベル連打です。ここは毎回おなじみの仕切りです。
今回、私が興味深いなと思ったのは、去年に比べてハコモノ、サードプレースネタが少ないです。サードプレースに至ってはゼロです。気になる人は、発表一覧をリストアップした去年のブログをご覧ください。
ハコモノ系に変わりコンテンツ系が多かったです。これを地域活性のトレンドがハードウェアからソフトウェアに変わったとみるか、コロナ下で学生生活を送った学生さんの着眼点が移っただけなのか。再来年以降の先々の話ですが、コロナ下の影響を受けなかった学生さんは、再び興味関心がハードウェアに移るのか引き続き興味関心を持っていきたいと思います。発表テーマに「多様性」という言葉が入ったのは初めてかも?今回、参加したゼミ生さんからの質問が多かった印象を受けましたが、テーマが自分事として考えやすかったのでしょう。
毎回発生することですが今回も「ああ、やっぱり」という出来事がありました。それは「若者の『問い』に地域が答えられないリアル」です。このフレーズは恒例になってしまうくらい卒論発表会のブログに書いています。私が発表内容を聞いていると疑問に思い、質問タイムで確認したところ「かくかくしかじか(自主規制)」「あー・・・」みたいな状況です。具体的に書くといろいろなところに飛び火しそうなので伏せます。私から言えることは「大人は学生をなめるな」でしょうか。適切な指導を受けて学んだ学生さんの問いに答えられない地域は若者から見捨てられると思います。
地域の地盤沈下が止まりません。ここ数年毎回、小笠原ゼミの卒論発表会に参加させて頂いていますが、年を追うごとに地域の質が低下していることを実感します。これは書かない(伏せた)方がいいなというエピソードや、これは前回のブログで書いたなというエピソードがあり、ブログの文章量が減っていきます・・・。
コロナ下の学生生活で学び続け、レア出現率の低いヒアリング先ガチャを乗り越え、卒論をまとめた発表者のみなさんお疲れさまでした。
小笠原先生、小笠原ゼミのみなさん、ありがとうございました。